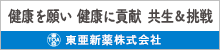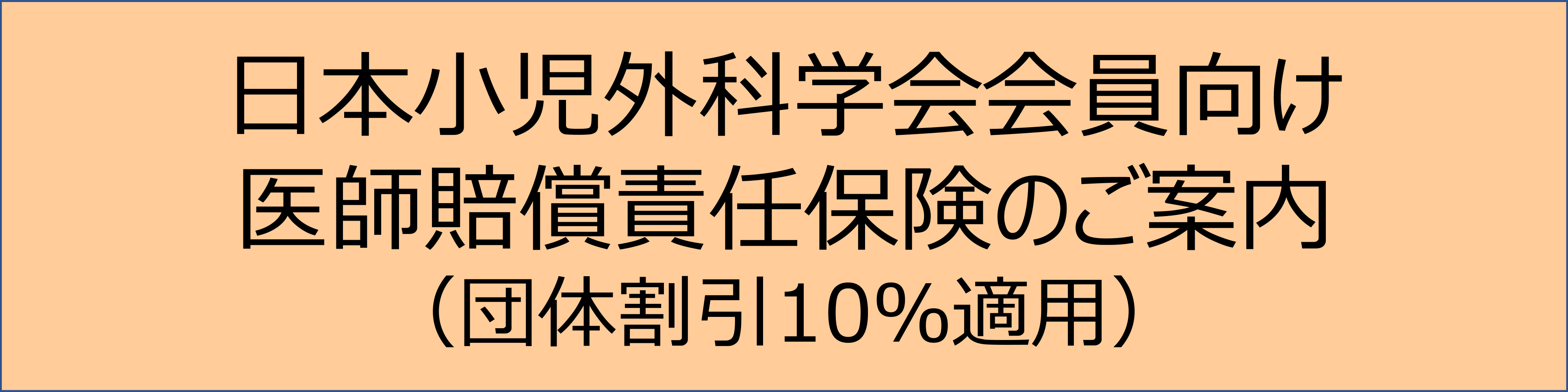好奇心旺盛だった幼少期
父が勤務していた小さな診療所に、就学前から入り込んでは、手伝える仕事がないかと待合室や調剤台のまわりをウロウロしていた。

後にその診療所では、手術や入院も受けつけるようになった。手術中は絶対に中を見てはいけないとわかっていながら、腰椎麻酔の様子をのぞいたこともある。切除された臓器を見せてもらったが、ほとんどがAppendixかhemorrhoidだった。
つまり、私には手術室がとても身近にあったのだ。かつ、何となく神聖な場であることも感じていた。
医学生時代に出会った小児外科
長崎大学医学部に入学したのは1975年。大学6年間は、軟式テニス部に所属し、大いに青春を謳歌した。
大学5年の外科の臨床実習で受け持った患者は、胆道閉鎖症であった。すでに、4ヵ月を過ぎて、腹水がたまり黄疸も進行していた。手術後も減黄に至らず、彼は亡くなった。
実習後も気になって、何度か病室を訪れ、小児外科の先生とも話す機会があった。その夏休みは、小児外科で実習をさせてもらい、ちょうど大分であった九州小児外科研究会にも参加できた。そこで、当時、留学から帰国して数ヵ月の水田祥代先生に初めてお会いした。
長崎大学では外科に女性がまだ受け入れられていなかったが、もしかすると、小児外科ならば……と勇気がわいたのは確かである。また、当時、九州には池田恵一先生や矢野博通先生など日本における小児外科の礎を築かれた素晴らしい先生方がいらした。
卒後20年目の転機
卒業後、地元には残らず、東京女子医大一般外科と聖隷浜松病院で研修し、長崎大学に戻った。この4年間、消化器外科や胸部外科などを広く研修し、最終的に、小児外科を目指すことに決めた。専門医資格取得のために上京し、国立小児病院で3年間のレジデントを経て、また長崎に戻った。
大学病院では、診療以外に、学会発表・教育・研究という使命がある。一時は、頑張って女性教授を目指すという目標が頭にちらついたこともあったが、自分でその能力も資質もないことはわかっていた。
そうしているうちに、卒業して20年をむかえようとしていた冬、病院の廊下の掲示板で一枚の小さいチラシを見つけた。『あなたを待っている人たちがいます』とあった。よく見ると、国境なき医師団(MSF)日本の海外派遣スタッフ募集説明会の案内である。すぐ、近くの公衆電話のダイヤルを回した。説明会は4日後。指示どおり、履歴書と志望動機をファクスで送った。翌日、「説明会に来られたら、面談をします」との返信があった。
月曜日の予定手術を終えて、JRで会場へ。説明会はすでに始まっていたが、会場に入ることなく、外のロビーで面接を受けた。面接官はフランスから来日していたリクルート担当者である。30分ほど話しただろうか。話すうちに、海外での医療・人道援助活動に参加するんだという確信に似た気持ちに変わっていた。2000年12月半ばのことであった。
ただ、本当に派遣されることが決まったのは、2ヵ月近く経ってからのこと。所属の教授に確認したところ、「どうしても国境なき医師団(MSF)での活動を希望するのであれば、大学を辞職して下さい」と言われ、あっさり従った。
新たな挑戦への一歩
翌年3月末日、大学医学部講師を辞職し、小雨の降る日の早朝5時、大きなスーツケースを引いて空港行きのバスに乗った。不安がなかったかと言えば、嘘になる。それまで、すべて自分で決断し、同僚・友人・家族には事後報告だった。今でも、「大学病院での地位を捨ててまで……」、「理解できない」という質問をされる。
しかし、多くの人が支えてくれたからこそできたことなのだ。12年を経た今、あの決断は間違っていなかったし、いい選択だったと胸を張って言える。
MSFの活動終了後は大学病院の小児外科に戻る予定だったが、その必要もなくなり、スリランカ滞在を1ヵ月延長した。帰国後に長崎で知人たちが開いてくれた報告会には、私が手術をした子どもたちが、お母さんたちといっしょに遠くからも聞きに来てくれた。私の小学校時代の友人のお母さんたちなど思いがけない人たちも集まって下さった。

紛争地で医療活動をすることが今ほど知られていない時代だったからかも知れないが、さまざまな形でこのような支援をして下さる方々の存在に感謝し、私はまた、この活動を続けていこうと決意した。
途上国での小児外科
今、国内で外傷外科という領域が独立しているところはない。私は、女子医大でも長崎大学でも消化器や胸部の外科を学んでいた。小児外科という領域でも、腹部や胸部に加え、当時は脊髄髄膜瘤や泌尿器系も手術していたので、途上国でも適宜対応できた。
初回のスリランカ4ヵ月滞在中には、北部のジャフナに2週間派遣された。ここには大きな大学病院があり、外科の教授が小児外科症例を集めていた。そこで、4歳の横隔膜ヘルニアや低位鎖肛の乳児などの手術をし、医学部5年生に小児外科の講義をした。また、オーバーヘッドプロジェクターを使って、新生児奇形の主な疾患を説明し、出生前診断などにも触れた。
ただ、15年以上も紛争が続いていたこの地域では、大学病院といっても、先天奇形の子どもを診断して手術できるレベルではなく、社会環境も整ってはいなかった。講義では「早くこの国の紛争が解決して、あなた方の中の誰かが小児外科医として活躍し、助かる命を救える環境になることを期待している」と締めくくった。
その1ヵ月前、もともと派遣されていた東部の病院で、私は小児外科手術をしていた。ある日、出勤すると、腹痛発作の10歳女児が入院していた。夜間に搬送されてきたという。病歴と臨床症状から胆道拡張症を疑い、産科のエコーで見ると、間違いなかった。
ただし、私たちMSFがここで対応していた症例は、戦傷外科が6~7割だった。午前中に限り、一つのオペ室でできる鼠径ヘルニアや下肢静脈瘤などの手術をしていた。この女児は絶食・点滴で膵炎症状が改善したら、退院させて、ちゃんとした設備のあるコロンボで手術をしてもらおうと考えた。
ところが、チームの仲間が、「せっかくこの手術ができるNOBUKOがいるのだから、ここでやったら……」「予定手術は延期できるから……」と言う。当時、紛争の真っただ中だったスリランカで、他民族を抑圧しようとしている地域の病院に行って手術を受けられるはずはなかった。
思い切って手術をすることにした。手術中に急な雨と雷で一時停電し、電気メスはカットのみで凝固しないことに気づいて、研修医相手の手術は予想以上に苦労した。それでも、2時間以内で手術を終えた。
外に出たら、お母さんが泣きそうな顔をしている。「大丈夫ですよ」と話すと、隣にいた叔父と名乗る男性が「心配してはいません。先生に英語で直接お礼がいえなくて、泣いているのです」と言った。この時あらためて、“小児外科医でよかった”と思った。術後経過は思いのほか順調で、1週間で退院していった。
MSFでかけがえのない経験
その後、イラク戦争時の隣国ヨルダン、津波後のインドネシア、リベリア、ナイジェリア、紛争地のソマリアなどで活動し、東日本大震災では第1陣として現地に入った。また、2013年には内戦下のシリアにも赴いた。2010年からはMSF日本の会長として、組織運営にも関わることになり、たくさんの仲間と出会い、多くの事を学んでいる。
日本にいる患者さんのために働き続けることは、もちろん素晴らしいことだ。一方、人生の一時期に、医療にアクセスできないで苦しんでいる人たちのそばに寄り添って活動することで、何かを得られることは間違いない。

特に、十分とはいえない設備・物資のなかで、より多くの助けられる命を救うために、医療スタッフもそうでない仲間も一丸となって働く。その経験は、帰国してからも、別の意味で日本の医療に還元できると、私は信じている。そして、日本からより多くの人たちが私たちのような活動に挑戦していただくことを期待している。