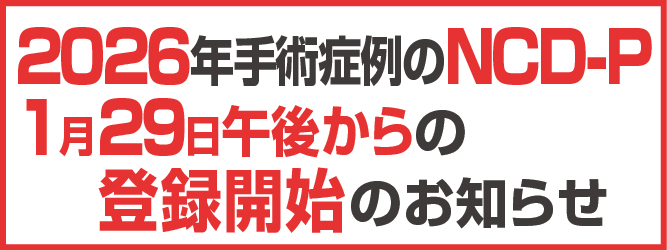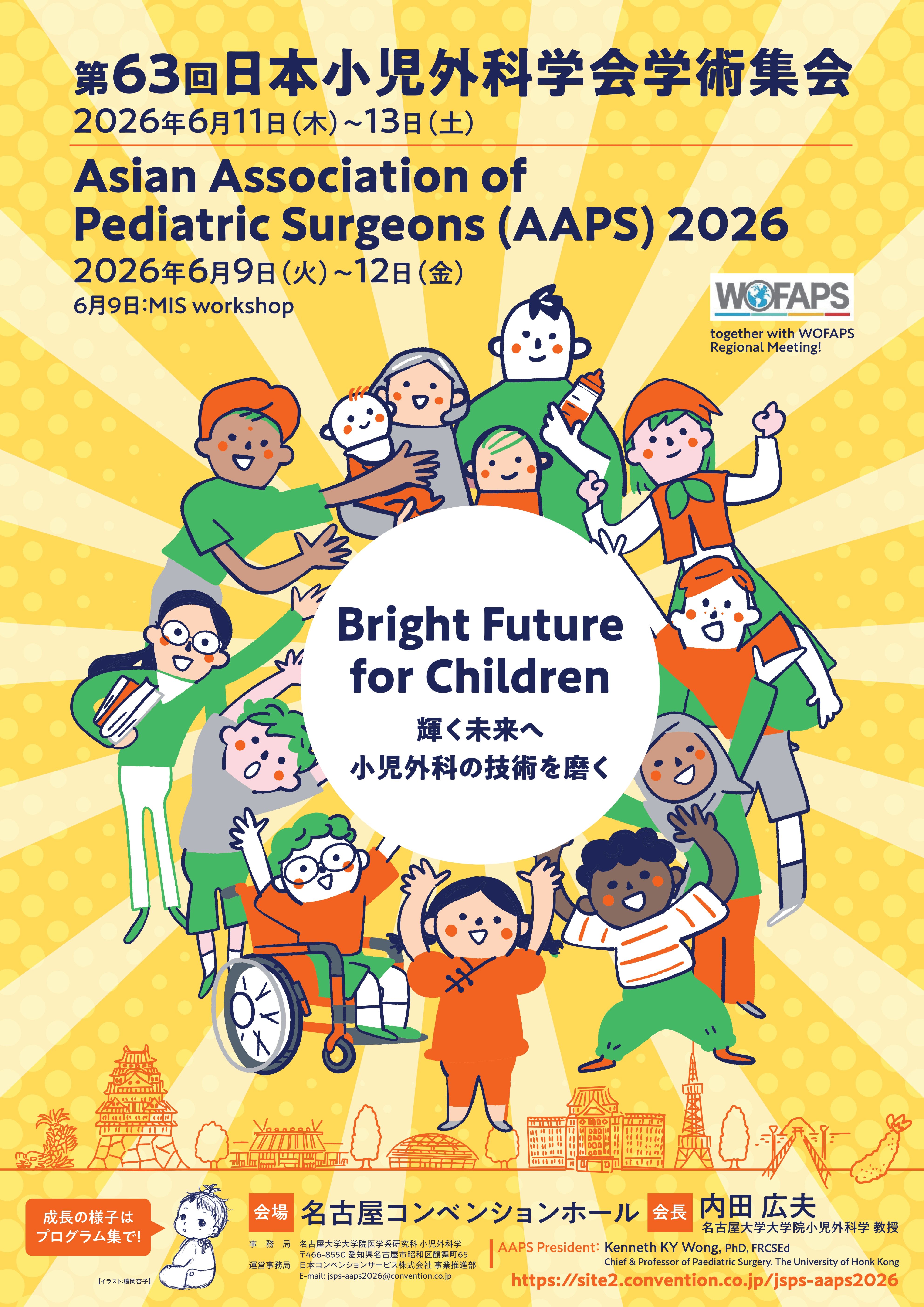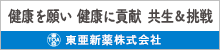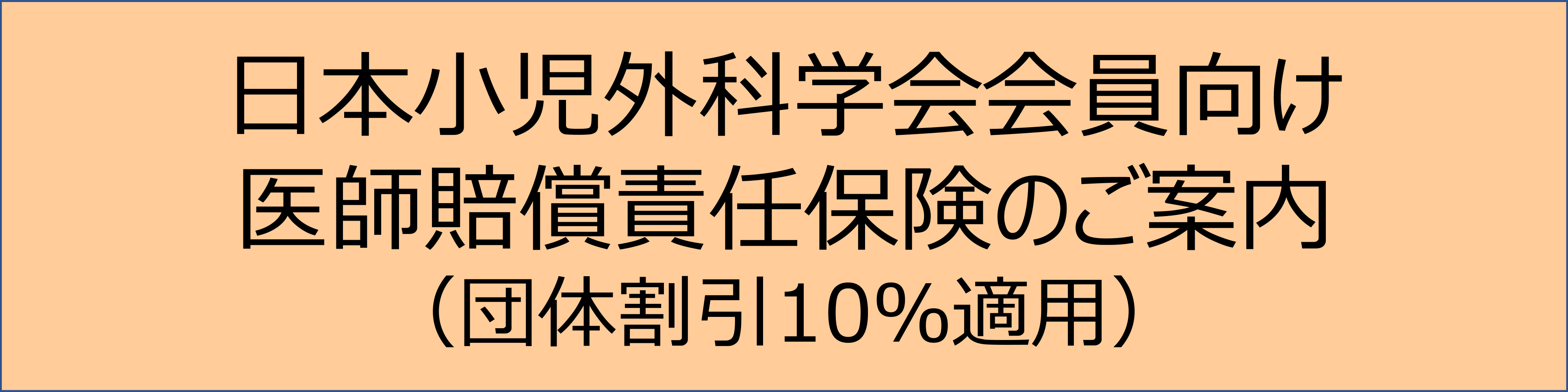FAQ
専門医・指導医の新規申請や専門医試験申し込みに際して,事務局に問い合わせがよくある質問とその回答を下記にまとめましたのでご参照ください.
研修期間等を含む受験資格に関しては,まずは施設長にご相談いただけますと幸いです.
【専門医新規】
| ① | 専門医申請する際に研修期間が丸3年必要ですが,研修期間をどこまで含めて良いのか知りたいです. 【回答】 専門医認定作業は,研修期間は年次報告に,症例数はNCD登録に基づくため,申請時点で年次報告NCD登録が確定している申請前年の12月分までしかカウントできません. |
| ② | 研修期間が充足しているかがわかりません. 【回答】 研修期間は各施設から提出される年次報告をもとに集計されます.研修期間が何カ月になっているかに関しては,施設長に年次報告で確認してもらってください. |
| ③ | 「小児外科専門医取得のための研修」というのは具体的にどういった条件でしょうか.小児外科に専従している期間のことという理解でよろしいでしょうか. また,外科専門医の研修中でも専従していた場合はその期間に含まれるのでしょうか. 【回答】 「小児外科専門医取得のための研修」は「常勤かつ専従している期間」のこととなっています.専従とは「外来,入院を問わず,小児外科の診療のみを行なっており,成人の診療には全く関与していない状態(当直勤務としてのみ成人の診療を行った場合は専従とする)」と定義されています. 外科研修中でも小児外科を専従している期間は研修期間としてカウントできますが,外科と兼任している期間はカウントできません. 各医師の勤務状況が「常勤」「専従」とみなすことができるかどうかは施設長が判断し,毎年の年次報告に登録されています.研修期間が何カ月になっているかに関しては,施設長に年次報告で確認してもらってください. |
| ④ | 新専門医制度で何度か説明されていた「小児外科専門医研修の開始宣言」というのが,どの時点のことなのかがわかりません. 【回答】 新専門医制度による小児外科専門医認定が始まっていないので,開始宣言はまだ始まっていません(2025年4月〇日時点). |
| ⑤ | 研修期間に含まれない期間においては,経験症例・執刀症例は専門医申請の際に活用できるのでしょうか.外科専門医においては初期研修での経験症例もカウントできましたが,小児外科専門医申請においては専従でない期間での経験症例はカウント可能でしょうか. 【回答】 現行の小児外科学会認定専門医の新規申請では,小児外科学会認定施設において小児外科領域手術としてNCDに登録されている手術がカウント可能です(初期研修期間中の経験症例も含まれます). 一方で,(まだ開始されていませんが)日本専門医機構が認定する新専門医制度下の小児外科専門医においては,専従の如何を問わず,初期研修中の登録症例はカウントされません. |
【指導医新規】
| ① | 「大学院、留学などの期間も臨床に携わり、この期間を外科医歴、小児外科医歴に換算される方は、臨床に携わっていることの証明できるもの(大学院であれば指導教官並びに臨床責任者の証明書、留学期間中であれば留学先の責任者の証明書)の提出を必要とします。」との記載がありますが、何か決まった様式がありますでしょうか。 【回答】 事務局側で用意した様式はありません. 指導教官ならびに臨床責任者に,大学院在学中や留学中にも臨床に従事していた旨を記載いただき、書類を提出してください.認定の可否は委員会で判定されることをご承知おきください. |
| ② | 論文が採択されましたが,申請までにHP上での公開が間に合いません. 【回答】 著者校正としてのPDF原稿や採用通知書など論文を審査できるものを提出してください.審査対象として受理したうえで,論文の内容を委員会で審議し て認定の可否を判断いたします. |
【専門医新規申請,指導医新規申請での麻酔種別について】
| ◆ | NCDでは「専門医・指導医新規申請」,「専門医・指導医更新申請」,「年次完了報告」によって,また「新生児症例」か「非新生児症例」かによって,手術と認定される麻酔の種別が異なっておりますのでご留意ください(下記表). |